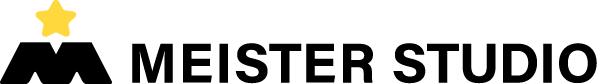社会課題への取り組み
ミライロのこれからと新しい応援のかたち
(ミライロ × マイスタースタジオ対話取材)
ミライロのこれからと新しい応援のかたち
(ミライロ × マイスタースタジオ対話取材)

デジタル障害者手帳「ミライロID」を中心として様々な障害者関連サービスを展開し上場を果たした株式会社ミライロ。今回は代表取締役社長の垣内俊哉さん、取締役副社長の民野剛郎さんと弊社寿倉で、対話形式でお話を伺いました。
私たちマイスタースタジオでは、社会課題の解決を目指すソーシャルビジネスに対し、内部留保の一部を「社会的投資」として活用し、連携・協力を進めています。本記事はその一環として、ミライロIDやユニバーサルマナー検定の社会的価値と今後の展望を、ユーザーや個人投資家の皆さまに広く知っていただくことを目的としています。
PROFILE
プロフィール

垣内 俊哉
株式会社ミライロ 代表取締役社長
1989年生まれ。骨形成不全症という遺伝性疾患のため、幼少期より骨折が多く、車いすでの生活を送る。2010年、立命館大学在学中に株式会社ミライロを設立。障害者や高齢者のサポート方法などを伝える「ユニバーサルマナー検定」や、障害者手帳をデジタル化した「ミライロID」など、障害者をはじめ多様な方々に向けたサービスを展開している。著書に『バリアバリュー 障害を価値に変える』(新潮社)、『自分の強みの見つけかた』(KADOKAWA)、『バリアバリューの経営』(東洋経済新報社)がある。

民野 剛郎
株式会社ミライロ 取締役副社長
1989年生まれ。立命館大学経営学部に在学中、垣内とともに社会性と経済性を両立するビジネスプランを考案し、国内で13の賞を獲得。その賞金をもとに、2010年に代表の垣内とともに株式会社ミライロを設立。障害を価値に変える「バリアバリュー」という理念のもと、企業や自治体、教育機関におけるユニバーサルデザインのコンサルティングを手がける。国内最大の障害者パネルを有する「ミライロ・リサーチ」や、遠隔手話通訳サービスを提供する「ミライロ・コネクト」など、複数の新規事業の起ち上げや、Airbnbのアクセシビリティ向上ワーキンググループ委員等を務める。

寿倉 歩
株式会社マイスタースタジオ 創業者
ソーシャルグッドリンク 代表
1982年大阪生まれ。立命館大学経営学部卒。メディアや証券、保育など様々な業界を経験後、アフィリエイトASPを運営する株式会社ウェブシャーク(現Yogibo)初期に参画、株式会社マイスタースタジオ設立、株式会社テミスホールディングス(現ラッコ)のメディア事業を管掌、同社取締役を経て、社会を良くする商品・サービスを広げることを目的とした成果報酬型の広告プラットフォーム ソーシャルグッドリンクを創業、同社代表を務める。
ミライロIDが生まれた理由と社会的インパクト
ミライロIDが生まれた理由と
社会的インパクト
寿倉
まずはミライロIDについて簡単に教えていただけますでしょうか?

垣内
私が障害者手帳を交付されたのは4歳のときなのですが、実は日本には292種類もの障害者手帳があり、この多さが事業者にとって確認の手間になっています。また、当事者にとっても、カバンから手帳を取り出すこと自体が心理的なハードルになるんです。
そこで、事業者側の手間と当事者の負担を減らそうという発想から生まれたのが「ミライロID」です。
当初は、292種類の手帳をひとつの形式に統合することが目的でしたが、今では顔認証との連携なども進んでおり、「292を1に」、さらに「1を0にする」ような世界の実現を目指しています。

寿倉
その「1を0に」というのは、非常に本質的ですね。
実は、弊社の妹尾も私も、友人や家族としてミライロIDにお世話になっています。
手帳を出すという行動は、当事者や近しい人にしかわからないかもしれませんが、
どこか申し訳ないような、でも同情されたくないような、言葉にしにくい複雑な気持ちになってしまい、つい気後れしてしまう場面があるんです。
でも、ミライロIDがあったことで、それを気にせずスムーズに利用できた──
そんな体験が、私たちの身近でも確かにありました。
寿倉
ビジョンの実現度合いとして、現在何合目に来ていると感じていますか?
垣内
正直に言うと、まだ3合目くらいですね。
連携している企業も、初年度の6社から今では4,100社以上に拡大し、自治体との連携も350を超えています。
ただ、日本には1,724の自治体があるので、まだ全体の1/5に過ぎません。制度連携や利用シーンの拡大など、外部環境の整備も含めて、まだまだ課題が多いと感じています。
寿倉
ありがとうございます。すでに多くの方が実際の場面で助けられている印象でしたが、まだ3合目というお話に少し驚きました。
ちなみに、ビジネス面で見たとき、ミライロ全社の中でミライロIDはどのような役割を担っているのでしょうか?

民野
もともと私たちは、ユニバーサルデザインやバリアフリーのコンサルティング事業からスタートしました。ただ、それだけでは、 障害のある方々に直接価値を届けるには限界があるという課題がありました。
そこで垣内が以前から思い描いていた「障害者手帳の電子化」に取り組み、誕生したのがミライロIDです。
特に鉄道事業者の導入が進んだことで、利用者数は10万、20万と拡大し、それに伴って、企業との連携による広告やクーポン配信などが収益源として立ち上がり始めました。
とはいえ、マネタイズはまだまだこれからです。今後はAPI連携などを通じて他の事業者との接点を増やし、機能や価値をより多くの企業に知ってもらうことで、収益モデルを強化していきたいと考えています。
海外展開と日本制度の強み
海外展開と日本制度の強み

寿倉
現在、海外展開の準備も進められていると伺っています。
各国の障害者手帳制度や文化的背景について教えていただけますか?
垣内
日本の障害者手帳制度は1949年に始まり、70年以上の歴史があります。制度設計の細やかさや深みという点では、海外とはまったく違います。
たとえばアメリカでは、州ごとに制度がバラバラですし、EU圏でも統一された仕組みはありません。アジアでも台湾・韓国・中国などで制度はありますが、形式はそれぞれ異なります。
台湾の障害者手帳などは、ラミネート加工されただけの簡易的なもので、不正使用が可能な状態なんです。
そうした現状の中で、日本の障害者手帳制度で培われた信頼性と仕組みを、私たちが海外に展開・運用していくことで、世界中の障害者がもっと自由に社会で活躍できる環境を整えたいと考えています。
寿倉
そもそも、障害者優遇制度そのものがない国もあるんですよね?
垣内
はい。たとえば電車の割引制度なんて、 すべての国や地域で整備されているわけではありません。まして一部の開発途上国では障害者支援の法制度が未整備です。制度があっても、周知・運用されていない国もあります。
寿倉
それは意外です。てっきり、どの国にもあるのかと思っていました。
垣内
「優先乗車」や「広いスペースの確保」といった物理的な配慮はあっても、料金を割り引くような金銭的優遇を設けている国は 決して多くありません。
多少の税制優遇がある程度で、民間事業者が自主的に割引を提供するという発想自体、あまり理解されません。
日本では、旧国鉄時代に始まった障害者割引を、補填もない中で70年以上にわたって民間事業者が自主的に続けてきた。これは本当に誇るべき文化だと思っています。
垣内
他国で同じことができない最大の理由は、「本人確認の仕組み」が整っていないからです。
身分証明がしっかりしていなければ、優遇制度そのものが成立しません。
だからこそ、ミライロIDが世界に広がっていけば、本人確認がスムーズになり、それを基盤に世界中で優遇制度が生まれていく可能性がある。私たちは、そう信じてステップを踏んでいるところです。
寿倉
手帳制度が存在しない国でも、ミライロが独自にサービスを展開すれば、「手帳がなくてもミライロIDがあれば優遇を受けられる」という仕組みが実現できますね。
垣内
まさに、そういう方向を目指しています。
実は偶然にも、ルーブル美術館やエッフェル塔で、ミライロIDが通用したことがありました。
「これは日本の障害者の身分証明書です」と伝えたら、「OK」となったんです。
相手国のオペレーションが厳しくなかったという偶然もありますが、重要なのは、世界に対して「これは障害者の本人確認に使える」という信頼性を築いていけるかどうかです。
「このほうが便利だし、これで確認すればいい」と思ってもらえるような、国際的に通用する認証インフラとして定着させることが、私たちの使命だと思っています。
今回、電子認証の導入という1つの節目を迎えたことで、海外展開に向けた大きな第一歩が踏み出せたと感じています。
将来的には、日本の障害者が海外で、海外の障害者が日本で。
そんなふうに、お互いにサービスを受けられる世界を実現したいと思っています。
寿倉
これまで海外展開については漠然としたイメージしか持てていませんでしたが、いまのお話を聞いて、とても具体的にイメージできました。
日本発で世界を変える——そんな大きな前進になることを心から楽しみにしています。
マイナポータルとミライロIDの関係
マイナポータルと
ミライロIDの関係

寿倉
たとえば、マイナポータルなど行政のサービスが今後さらに進化していく中で、「ミライロIDが将来的に代替されてしまうのではないか」といった制度的・事業的なリスクについて、どのようにお考えでしょうか?
垣内
まず前提として、ミライロIDとマイナポータルはすでに連携しています。
少し仕組みをご説明すると──
ユーザーは、障害者手帳の情報をマイナポータルを通じてミライロIDに提供することに同意します。その後、マイナンバーカードを使ってマイナポータル(政府の情報提供サービス)にログインすることで、本人確認を行います。それによって連携申請が行われ、自治体のサーバーからミライロIDが障害者手帳の情報を取得するという流れです。
ミライロIDの役割は、独自で持つ情報とマイナポータル経由で提供される情報を照合し、一致していれば連携済としてアプリ上に表示することにあります。マイナポータルとの連携により、情報の信頼性がより一層高まります。
また、ミライロIDの普及は、マイナポータルやマイナンバーカード等の行政インフラの利用機会の増加にも繋がります。
このように、両者は競合するものではなく、補完関係にあるんです。
寿倉
ありがとうございます。ということは、「将来的にマイナポータル側のアプリがミライロIDに取って代わる」といったようなリスクはないという理解でよいでしょうか?
垣内
はい、そのようなリスクはありません。
すでにマイナポータルとミライロIDは機能的に連携しています。
マイナポータルと連携されていることを、ミライロID側で表示する設計になっています。
両者が一体となって初めて、高い信頼性を有する障害者の身分証明の電子化が実現できていると言えます。
寿倉
ありがとうございます。よく理解できました。
この懸念が払拭されることは、長期的に応援したいと考える個人投資家の方々にとっても非常に重要だと感じています。
経営スタイルと二人の関係性
経営スタイルと二人の関係性

寿倉
ご著書などからも、お二人の関係性に強く惹かれました。とてもフラットで、お互いを尊重し合っている印象です。
実際、垣内さんはよく「民野のおかげ」とおっしゃっていますし、民野さんは「意見が割れたら最終的に垣内に従う」と、一歩引いたスタンスを取られているように感じます。
こうした絶妙なバランスは、どのように築かれてきたのでしょうか?
垣内
私自身が至らないところを民野が補ってくれているからこそ、ここまでやってこられたと思っています。
20歳前後で出会ってから、もう15〜16年。一緒に歩んできた中で、「こういう振る舞いは直すべきだ」といったことをお互いに率直に伝え合い、少しずつ高め合ってきました。
そうして積み重ねるうちに、お互いの思いや心情を深く理解できる関係になったと感じています。
「民野のおかげで」とよく言うのも、本当にそう思っているから自然と出るんです。
特に強くそう思ったのは、2016年に体調を崩して手術と長期入院を迷っていたとき。
民野に相談したら、すぐに「手術しろ、休め」と言ってくれて。実際、入院中も会社は民野を中心に、社員全員の力でしっかり成長を続けてくれました。
寿倉
垣内さんからの強い信頼が伝わるエピソードですね。
民野さんは副社長として、つらさや悩みを感じたことはなかったのでしょうか?
民野
もちろん、たくさんありましたよ(笑)。
ただし、一般的には、創業者がいて、その後に副社長が加わるケースが多いと思いますが、私たちは最初から一緒にスタートしています。
No.2という立場にはどの会社にも難しさがあると思いますが、私たちは「友人」から始まり、立場としても同じ経営者でした。
そのせいか、見るべき視点や視座も自然と共通していましたし、私自身はかなり負けず嫌いなので、むしろ「垣内より強い気持ちで経営するぞ」くらいの意識でやっていました。
だから「社長がこうだから」といった不満は起きにくかったです。
むしろ、垣内が何かできていなければ「それは自分の責任でもあるかもしれない」と、あるときから思えるようになりました。
過去には不満を口にしていた時期もあったかもしれませんが、今はもう、そういう感情はありませんね。
垣内
民野は、経営やビジネス、戦略といった部分に強みがあり、私は「人にどう伝えるか」「さまざまな人とどう関係を築くか」というところに関心があります。
そうした違いが、これまでの時間の中で自然と役割分担につながっていったように思います。
寿倉
お二人は大学時代に出会い、友人関係から経営のパートナーになられたと伺いました。
最初から、お互いのタイプや役割の違いを意識されていたわけではないですよね?
垣内
そうですね。心の根っこの部分で通じ合っていたからこそ、一緒にやろうと思ったのが出発点です。
お互いの特性や強みは、役割を整理していく過程で自然と引き出されていった感じです。
ちなみに、「社長・副社長、どっちがやる?」という話になったとき、2009年5月28日、南草津のお好み焼き屋で、民野が「この事業をやるなら垣内だろう」と言ってくれて。それで私が社長に決まりました。
もしやっていた事業が違っていたら、民野が社長になっていたかもしれませんね。
寿倉
親友であり、経営パートナーというのは本当に最高の関係ですね。
弊社でも、社長は妹尾や私の固定ではなく、数年ごとに交代してもよいくらいの感覚で経営しています。
実は私自身も、過去にメニエール病を頻繁に発症したり、中度まで進行した緑内障の診断を受けたりした経験がありまして。そうしたこともあって、垣内さんのご入院中に民野さんが会社を支えられたというお話を伺い、あらためて「どちらかが倒れても事業が続けられる体制」を整えることの大切さを実感しています。
個人投資家との関係と「共感の資本」
個人投資家との関係と
「共感の資本」

寿倉
では最後に、個人投資家の方々へのメッセージをお願いします。
ミライロIDやユニバーサルマナー検定など、社会課題の解決を目指す事業を応援してくださっている投資家の皆さんと、どのような関係を築いていきたいとお考えでしょうか?
垣内
2024年3月24日の上場以降、私たちは毎週1〜2本のIR(投資家向け情報)を継続的に発信しています。
決算情報や業績に加え、私たちが「どう社会を変えていこうとしているのか」という視点も、丁寧に伝えていきたいと考えているからです。
私たちは、「共感という資本」を、多くの方々からいただいています。
たとえば、上場直後の4月、モーニングサテライトで車いすで上場の鐘を打つ私の姿が放送された際には、X(旧Twitter)やFacebookなどに、多くのメッセージが寄せられました。
障害のあるお子さんを育てているお母さん方から、
「ずっと応援していました」「涙が止まりませんでした」「ミライロの株、買いました」──
そんな声がたくさん届いたんです。
もちろん、株を買ってくれたかどうかにかかわらず、見守ってくださっていること自体が本当にありがたいと感じています。
私たちの責任は、そうした共感を寄せてくださる皆さんに対して、伝え続け、見せ続け、結果を出していくことだと思っています。
寿倉
IRでは、視覚・聴覚に配慮した情報保障にも取り組まれていますよね。

民野
はい。第2四半期の決算説明会では、手話通訳や文字通訳といった情報保障をしっかり付けました。これは非常に象徴的な試みだったと思っています。
あるご夫婦で、奥様がろう者という方がいらっしゃったのですが、その方が初めてご夫婦で決算説明会を一緒に視聴できたというお声もいただきました
これまで、投資家の中にも障害のある方は確実に存在していたはずです。
それにもかかわらず、十分な情報アクセスが提供されてこなかったのは、「公平な投資の機会」が与えられていなかったということ。これは大きな課題でした。
だからこそ、誰にとってもアクセス可能なIRを届けることは、ミライロとして果たすべき社会に対する責任だと思っています。今後も継続していきたいですね。
寿倉
ありがとうございます。
もちろん、投資家の関心には「値上がり益」や「配当」もあるとは思いますが、最近では「それだけではない」という価値観が広がりつつあると感じています。
先ほど垣内さんもおっしゃっていた「共感資本」という言葉に象徴されるように、お金との向き合い方について、どのようにお考えでしょうか?
垣内
そうですね。
「共感できる先にお金を託す」という行為は、突き詰めると「応援している自分が幸せだ」と感じられるから続くものだと思うんです。
投資も同じで、「この会社に投資している自分が誇らしい」「応援している自分が好き」と思えたら、短期的な利益にかかわらず、長期的な視点で関わっていただけるはず。
今で言うと、いわゆる「推し活」のようなものに近いかもしれません。
「本当に好きだから応援している」という感覚です。
でも、それを続けていただくためには、私たち自身がそれに値する存在であり続けなければならない。
「無条件で応援される」ことなんてありませんから。
だからこそ、自分たちをしっかりと磨き続ける責任があると思っています。
そしてもうひとつ──
お金を「どう使うか」という視点で見たときに、幸せなお金の使い方がとても大切だと考えています。
それを伝え、示していくことがIRの本質でもあるのではないでしょうか。
「私の応援によって、この会社が成長した」
「私の応援によって、世の中が少し変わった」
そう思ってもらえたなら、投資はもっと幸せな営みになると信じています。
寿倉
本当にその通りですね。
実は私たちも、会社の内部留保で眠っているお金を「社会的に活かす」ことができないかと考えていまして。
私たちだけが社会的投資を行っても微力かもしれませんが、そうした考え方に共感してくださる個人投資家の皆さんとともに、この投資スタイルを少しずつ広げていけたら、社会をまた一歩、前に進められるのではないか──そんなふうに感じています。
今回のこの記事も、そうした新しい価値観を届ける小さなきっかけになれば幸いです。
ミライロIDというアプリの素晴らしさは、上場前から存じ上げていました。
だからこそ、2025年3月24日の上場を機に、迷うことなく投資を決めさせていただきました。
それは、単なるビジネス的な判断ではなく、「この会社を応援したい」という素直な感情からのものでした。
垣内さんとは今回が初対面でしたが、経営者としての気迫と、人を包み込むような温かさが同時に感じられ、とても印象に残りました。
民野さんとは、共通の友人を通じてご縁をいただき、何度かお食事をご一緒する中で、ゆっくりお話しさせていただく機会もありました。穏やかで実直な語り口のなかに、社会を変えていくことへの揺るがぬ意志を感じ、そのお人柄に深く共感しています。
今回の対話取材を通じてあらためて、ミライロという企業が社会の制度とテクノロジーを結ぶインフラとして、確実に世界を前に進めていることを実感しました。
私たち自身、株主の一人として、また社会課題の解決に取り組む経営者の一人として、今後も連携させていただけることを心から楽しみにしています。
そして、もし本記事をお読みいただいた方の中で、少しでも共感いただける部分があれば、ぜひ株主として応援していただいたり、SNSなどでこの記事をご紹介いただけたらとても嬉しく思います。
あなたの共感が、社会を変える一歩になると信じています。